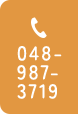網膜静脈閉塞症
網膜は眼底にある薄い神経の膜で、カメラのフィルムにあたる働きをしています。網膜血管は心臓から視神経内を通って網膜に酸素を供給する「網膜動脈」と、心臓にもどる「網膜静脈」から構成されています。網膜にある静脈が詰まった状態が網膜静脈閉塞症で、血液の流れが滞るため眼底出血や黄斑浮腫を起こし、視力低下の原因となります。高血圧があると発症しやすく、糖尿病や動脈硬化のある方もリスクが高いです。
網膜静脈閉塞症の種類
網膜静脈分枝閉塞症
網膜内には静脈と動脈が交差している部分があり、そこが閉塞を起こした状態です。眼底出血や網膜浮腫を起こしますが、閉塞部位の位置により自覚症状の程度は軽度のものから重度のものまで様々です。黄斑部に障害が生じると、視力回復が困難な場合があります。網膜中心静脈閉塞症よりも発生率が約4~5倍高いとされています。
網膜中心静脈閉塞症
視神経内にある静脈が閉塞した状態で、黄斑を含めた網膜全体に出血や浮腫が起こります。出血は時間の経過とともにおさまることが多いですが、出血の程度によっては視力低下が回復しない場合もあります。
網膜静脈閉塞症の症状
- 視力低下
- 視界が暗く感じる
- 視野が欠ける など
網膜静脈閉塞症の検査
- 視力検査、眼底検査
- 光干渉断層計(網膜の層構造を断面的に観察する検査です。黄斑浮腫の程度を評価します)
網膜静脈閉塞症の治療
硝子体注射
黄斑浮腫のために視力低下をきたしている場合に行います。主に抗VEGF薬を注射しますが、ステロイド薬を眼球の外側に注射する場合もあります。
薬物療法
網膜の血液循環を改善する薬などを状態に合わせて処方することがあります。
網膜光凝固術
黄斑部の浮腫が引かない場合や、病変範囲が広い場合は硝子体出血や牽引性網膜剥離を予防する目的で、レーザー光による網膜光凝固術を行います。
硝子体手術
硝子体出血や網膜剥離を生じた場合には、硝子体手術を行うことがあります。
※多くの場合高血圧や動脈硬化が原因となることがあり、糖尿病などもリスクを高める一因となります。50~60代の中高年に生じることが多く、好発年齢は60~65歳です。眼科治療と同時に高血圧、高脂血症、動脈硬化といった基礎疾患に関する精査・加療を行うことも重要です。
網膜動脈閉塞症
網膜を栄養する動脈が詰まることで、網膜の細胞への血流が途絶え視力低下を引き起こします。網膜の動脈は眼球の後方にある視神経内を通り、網膜全体に広がっています。動脈が詰まると網膜には血流が流れなくなり、1~2時間で網膜の細胞が壊死してしまいます。血流が途絶えた網膜は光を感じることが出来なくなり、急激に視野全体または一部が見えなくなります。
網膜動脈閉塞症の種類
網膜動脈分枝閉塞症
網膜動脈の1部分が閉塞する
網膜中心動脈閉塞症
網膜の中心動脈が閉塞する
網膜動脈閉塞症の症状
- 視力低下
- 視界が暗く感じる
- 視野が欠ける など
網膜動脈閉塞症の検査
- 視力検査、眼底検査
- 視野検査(見える範囲を確認します)
網膜動脈閉塞症の治療
現段階では確立された治療法はありませんが、次のような治療が代表的です。
眼球マッサージ
まぶたの上から指で眼球マッサージを行い、網膜血管の循環を促します。
前房穿刺
眼球の中の水分を排出して眼圧を下げる治療です。眼圧を下げることで網膜血管を拡張する目的で行います。
薬物療法
眼圧を低下させるための点眼薬や、血栓溶解剤、循環改善薬、高浸透圧利尿薬などを投与します。
※網膜細胞が動脈閉塞による虚血に耐えられるのは1~2時間です。この時間内に閉塞を解除し、血流を再開することが出来ないと視力低下や視野障害の回復が困難となります。症状改善の程度は、発症時の血管閉塞の程度と治療開始までの時間により様々です。
頸動脈の動脈硬化により形成された血栓や、不整脈などで生じた血栓が血流にのって運ばれることで動脈閉塞を引き起こすことが多いです。眼科治療と同時に内科医と連携をとり、採血・心電図や頸動脈エコーなどを行い治療を進めていく必要があります。