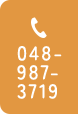健康診断や人間ドックで要再検査となった場合
健康診断や人間ドックにて行われる眼科検査の項目で「要再検査」と指摘を受けた場合、なるべく早めに眼科を受診しましょう。何らかの疾患を発症している可能性もあり、その場合は早期発見・早期治療が欠かせません。
健康診断で指摘される主な症状・疾患
高眼圧
高眼圧とは眼圧(眼の硬さ)が正常値の10~21mmHgを上回った状態です。
この状態が持続すると、視神経がダメージを受けて緑内障を発症する可能性があります。
視神経乳頭陥凹拡大
視神経乳頭とは視神経が束となり脳に向かうため、眼球壁を突き抜ける部分です。視神経乳頭陥凹拡大とは視神経乳頭の陥凹した部分が通常よりも大きくなった状態です。健康診断の眼科検査にて、一番よく指摘されます。
視神経が傷害されていた場合には、視野欠損(緑内障)が生じている危険性があります。
網膜神経線維層欠損
視神経乳頭から眼球内に広がる視神経線維が損傷して欠損した状態です。視野欠損(緑内障)の危険性があります。
黄斑変性
黄斑変性が疑われた場合は、下記の疾患が認められることがあります。
加齢黄斑変性
加齢黄斑変性は物を見る上で最も重要な役割を果たす黄斑が変性する疾患です。主な原因は疾患名のとおり加齢です。視力低下、視界の歪み、視界中央部のぼやけ、中心暗点などの症状が起こります。加齢黄斑変性は萎縮型と滲出型に分かれますが、滲出型は急激に症状が進みます。重症化した場合、失明するリスクもあるので、早期発見・早期治療が欠かせません。
黄斑上膜(黄斑前膜・網膜上膜・網膜前膜)
黄斑上膜は黄斑の前に薄い膜ができる疾患です。網膜と水晶体の間にはゼリー状の硝子体という組織がありますが、加齢に伴って縮んでいき硝子体から剥離します(後部硝子体剥離)。この過程で硝子体の一部が網膜表面に残り膜を形成します。
黄斑上膜は突発性と続発性に分かれます。続発性の原因はぶどう膜炎、網膜剥離(手術後に起こることも)、外傷などが挙げられます。
悪化した場合、視力低下や視界の歪みなどの症状が起こります。
眼底出血
眼底出血とは眼底の網膜を走る血管から出血が発生した状態です。主な原因には高血圧や糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、加齢黄斑変性症、網膜剥離、網膜裂孔などが挙げられます。眼底出血が起きた場合、網膜が浮腫んで視界の歪みや視力低下、飛蚊症などの症状が現れます。また新生血管が形成されますが、非常に脆いため出血が起こりやすい状態です。
視力低下
裸眼・矯正視力が低下した状態を指します。
眼科疾患が原因となることも多く、視力が低下している場合は疾患の可能性も踏まえて検査を行います。
中間透光体混濁
目に入った外部の光は角膜→水晶体→硝子体→網膜の順に届きます。中間透光体は角膜・水晶体・硝子体の総称で、網膜に光を届けています。
通常、中間透光体は透明ですが、何らかの原因により中間透光体が濁った状態を中間透光体混濁と言います。原因は様々考えられますが、なかでも白内障が原因となることが多いです。その他の原因として角膜障害や硝子体出血などが挙げられます、
動脈硬化・高血圧性眼底
高血圧では、網膜の動脈が細くなる、動脈の太さに差異が発生する、視神経乳頭の腫れ、出血、白斑などが認められることがあります。動脈硬化が起こると動脈の色調が変化したり、動脈と静脈が交叉する部分が圧迫したりすることがあります。その結果、血管の損傷が悪化した場合、網膜動脈閉塞症・網膜静脈閉塞症といった視力低下を招く深刻な疾患に繋がるリスクが高まります。なお高血圧や動脈硬化は自覚症状が乏しいため、定期的な検査が欠かせません。
生活習慣と眼科疾患の関係性
眼科疾患は多岐にわたりますが、糖尿病や高血圧など基礎疾患の有無だけでなく、生活習慣と関係が深いものも多くあります。この「生活習慣」には、食事や運動、睡眠だけでなく、パソコンやスマートフォンなどの利用による眼の酷使なども該当します。
次のような症状、お悩みを抱えている方は、一度当院までご相談ください。
- 目が重い気がする
- 目や目の奥に痛みを感じる
- 目が乾く、ゴロゴロする、ショボショボする
- 生活習慣が乱れており、眼科疾患を発症しないか不安
- 仕事でパソコンを長時間見続けて目を酷使している
- 生活習慣を改善して目の健康を維持したい
- 生活習慣病(高血圧症や糖尿病など)と診断された
- 糖尿病網膜症を発症している
お子様の目の相談
当院では成人だけでなくお子様の目に関する相談も受け付けています。
次に示すような症状や様子が確認される場合、あるいは学校健診で目について異常を指摘された場合、一度当院までご相談ください。
- 目を頻繁に擦っている
- 目やにや目の充血が確認できる
- 常に涙目になっている
- 目を細めたり、片目をつむったりする癖がある
- まばたきを頻繁にしたり、強く目をつむったりする癖がある
- 片目を使って物を見る癖がある
- 寄り目になっている
- テレビを近い距離で見ている
- 眼鏡を作成したい
- コンタクトレンズを作成したい
学校健診について
視力検査
学校で行われる視力検査では、「370方式」という方法が採用されています。この方法は短時間で視力検査を行え、判定はA~Dで出ます。養護教諭などが検査を担当するため、予備的な検査の位置づけとなります。
| ランドルト環(※)の見え方 | 教室での黒板の見え方 | |
|---|---|---|
| A判定 | 1.0の大きさがはっきりと見える | 後ろの席でも文字がはっきりと見える |
| B判定 | 0.7の大きさははっきりと見える | 後ろの席でも文字をある程度読める |
| C判定 | 0.3の大きさははっきりと見える | 後ろの席では見えづらさを感じる |
| D判定 | 0.3の大きさはぼやける | 前の席でも見えづらい |
※ランドルト環:視力検査でよく用いられる「C」のようなマークです。
視力検査の判定について
両目の判定に2段階以上の差が出ている、例えば「右目はA判定で、左目はC判定」といった場合、なるべく早めに眼科を受診しましょう。
当院では眼鏡やコンタクトレンズの処方だけでなく、
リジュセアミニ点眼、オルソケラトロジーなど、近視進行抑制治療も行っております。詳しくは検査・診察時にご質問ください。
眼鏡の作成について
当院では眼鏡処方を行っております。詳しくは検査・診察時にご質問ください。
コンタクト処方について
当院では、中学生以上の方を対象にコンタクトレンズの処方を行っています。未成年の方は保護者の同伴が必須となります。コンタクトレンズの管理・装用に関して丁寧にお伝えします。
当院の検査
眼圧検査
眼圧とは眼の内側から外側にかかる圧力のことです。眼圧が高い状態が続くと、緑内障の発症リスクが高くなると言われています。緑内障は失明の原因にもなる病気です。年齢、家族歴、強度近視、糖尿病、高血圧なども、緑内障のリスクを上げます。
逆に眼圧が正常でも緑内障になる場合もありますので40歳を過ぎたら定期的に検査を受けることをお勧めします。
眼位検査
眼位検査とは斜視の有無やその程度を調べる検査です。
斜視は両目の視線が合わない状態です。
斜視の原因には、先天的な神経・筋肉の異常、外傷、遠視などがあります。
斜視は眼科にて屈折矯正や視能訓練を行うことで改善が見込まれます。眼位検査にて異常を指摘された場合には、当院までご相談ください。
外眼部検査(結膜・角膜・まつ毛・まぶたの異常に関する検査)
外眼部とは眼球に付属する器官(結膜や角膜、まつ毛、まぶたなど)です。外眼部検査はこれら器官に起こる異常、例えば、ウイルス性・アレルギー性結膜炎、逆さまつ毛などの有無を調べます。これら疾患は治療せずにいると、視力低下などの原因となります。
色覚検査
カメラでいうフィルムに当たる網膜には、光を感じ取る「視細胞」があり色を認識します。この視細胞には光の三原色である赤・緑・青にそれぞれ敏感な3つの種類があります。この3つのうちどれかがうまく機能しないと、色が識別しにくくなり、この状態が「色覚異常」と呼ばれています。色覚異常は主に先天性のものが多く、種類や程度も様々ですが、決して白黒に見える状態ではありません。日本人での頻度は男性の約5%、女性の約0.2%にみられます。平成15年の法改正で、学校での色覚検査は必須項目から希望者への任意項目となりました。色覚検査のスクリーニングには「石原式色覚異常検査表」が用いられます。学校健診で異常を指摘された場合には、当院へご相談ください。各種色覚検査表の他に「パネルD-15」を用いて色覚異常の程度分類も行っております。