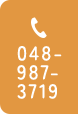糖尿病網膜症とは
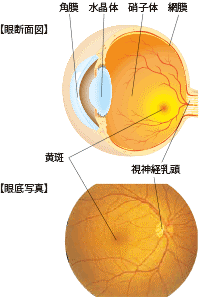 糖尿病網膜症は、糖尿病腎症・神経障害とともに糖尿病の3大合併症の1つです。網膜は眼底にある薄い神経の膜で、カメラのフィルムにあたる働きをしています。網膜には光や色を感じる神経細胞が敷きつめられており、その間に張り巡らされた無数の血管によって酸素と栄養が供給されています。血糖が高い状態が続くと、網膜の細かい血管が損傷を受け血流が悪化します。その結果、新しい血管(新生血管)が出来ますが、この新生血管はもろくて破れやすいため、壊れて出血し視力障害の原因となることがあります。また出血することで、増殖組織と呼ばれる、かさぶたの様なものが形成され、これにより網膜剥離を引き起こすこともあります。糖尿病網膜症は、糖尿病発症後10年以上経過してから発症するといわれていますが、初期段階では自覚症状に乏しいことも多いです。糖尿病と診断されたら、定期的な眼科受診をおすすめしています。
糖尿病網膜症は、糖尿病腎症・神経障害とともに糖尿病の3大合併症の1つです。網膜は眼底にある薄い神経の膜で、カメラのフィルムにあたる働きをしています。網膜には光や色を感じる神経細胞が敷きつめられており、その間に張り巡らされた無数の血管によって酸素と栄養が供給されています。血糖が高い状態が続くと、網膜の細かい血管が損傷を受け血流が悪化します。その結果、新しい血管(新生血管)が出来ますが、この新生血管はもろくて破れやすいため、壊れて出血し視力障害の原因となることがあります。また出血することで、増殖組織と呼ばれる、かさぶたの様なものが形成され、これにより網膜剥離を引き起こすこともあります。糖尿病網膜症は、糖尿病発症後10年以上経過してから発症するといわれていますが、初期段階では自覚症状に乏しいことも多いです。糖尿病と診断されたら、定期的な眼科受診をおすすめしています。
日本糖尿病眼学会 www.jsod.jpより抜粋
糖尿病網膜症の種類
進行の程度により3段階に分けられています
単純糖尿病網膜症
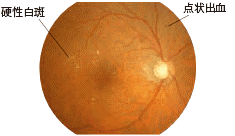 自覚症状を起こすことはほとんどありませんが、眼底検査をすると瘤のようになった毛細血管や点状出血、毛細血管から漏れたタンパク質や脂質の成分が網膜に沈着してできるシミのような硬性白斑などが認められることがあります。糖尿病治療で適正な血糖値を保つことで、改善する場合もあります。
自覚症状を起こすことはほとんどありませんが、眼底検査をすると瘤のようになった毛細血管や点状出血、毛細血管から漏れたタンパク質や脂質の成分が網膜に沈着してできるシミのような硬性白斑などが認められることがあります。糖尿病治療で適正な血糖値を保つことで、改善する場合もあります。
日本糖尿病眼学会 www.jsod.jpより抜粋
増殖前糖尿病網膜症
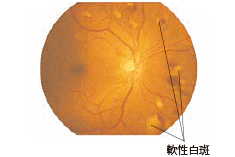 単純糖尿病網膜症が進行すると、毛細血管の閉塞範囲が広がり、網膜の中に酸素や栄養が行き渡らない部分が増えることで、もろくて壊れやすい新生血管が出来る準備が始まります。視力低下などの症状を認める場合もありますが、自覚症状がないこともあります。適正な血糖コントロールとともに、網膜光凝固術などの治療が必要になる場合があります。
単純糖尿病網膜症が進行すると、毛細血管の閉塞範囲が広がり、網膜の中に酸素や栄養が行き渡らない部分が増えることで、もろくて壊れやすい新生血管が出来る準備が始まります。視力低下などの症状を認める場合もありますが、自覚症状がないこともあります。適正な血糖コントロールとともに、網膜光凝固術などの治療が必要になる場合があります。
日本糖尿病眼学会 www.jsod.jpより抜粋
増殖糖尿病網膜症
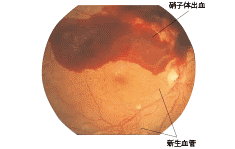 増殖前糖尿病網膜症が、更に進行して重症化した状態で、新生血管が網膜や硝子体に向かって伸び、壊れることで硝子体出血を起こします。新生血管の周りに増殖膜と呼ばれる線維性のかさぶたのような組織が出来ると、それが網膜を引っ張ることで網膜剥離を引き起こすことがあります。硝子体出血や網膜剥離は、急激な視力低下を引き起こし、適切な治療を行っても視力回復が困難となり、日常生活に支障が及ぶ場合があります。
増殖前糖尿病網膜症が、更に進行して重症化した状態で、新生血管が網膜や硝子体に向かって伸び、壊れることで硝子体出血を起こします。新生血管の周りに増殖膜と呼ばれる線維性のかさぶたのような組織が出来ると、それが網膜を引っ張ることで網膜剥離を引き起こすことがあります。硝子体出血や網膜剥離は、急激な視力低下を引き起こし、適切な治療を行っても視力回復が困難となり、日常生活に支障が及ぶ場合があります。
日本糖尿病眼学会 www.jsod.jpより抜粋
黄斑浮腫
網膜の中の黄斑部という物を見るために最も重要な部分に、むくみが起こる状態です。黄斑周辺の毛細血管の瘤や血管から染み出した血液成分などにより、むくみが引き起こされます。初期の糖尿病網膜症でも起こる可能性があり、視力低下の原因となります。
糖尿病網膜症の検査
 視力検査、眼底検査
視力検査、眼底検査- 光干渉断層計:網膜の層構造を断面的に観察する検査です。糖尿病黄斑浮腫の診断を行います。
糖尿病網膜症の治療
網膜光凝固術
レーザー光で網膜を熱凝固することで、新生血管の発生を予防したり、すでに出現した新生血管を減らしたりする治療法です。この治療により網膜全体のむくみが軽減され視力の改善が認められる場合がありますが、この治療は糖尿病網膜症の悪化を防ぐための治療であり、発症前の状態に戻すための治療ではありません。網膜症の進行具合によって、レーザーの照射数や範囲が異なります。将来の失明予防のために必要な治療です。
硝子体注射
抗VEGF薬を硝子体内に注射する薬物療法で、新生血管の発生や成長を抑制します。
網膜や黄斑部に生じたむくみの改善を促しますが、効果は一時的であるので、定期的に繰り返す必要があります。
硝子体手術
レーザー治療で網膜症の進行が予防出来なかった場合や、すでに網膜症が進行し硝子体出血や網膜剥離がおきている場合に行います。顕微鏡下で眼球に細い手術器具を挿入し、眼の中の出血や増殖組織を取り除いたり、剝がれている網膜を元に戻したりする手術で、高度な技術と経験が必要な手術です。
糖尿病と診断された方は定期検診が必要です
糖尿病網膜症は、進行するまで自覚症状がない場合も多いですが、病気が進行すると視力や視野の回復が困難となります。進行した網膜症の場合、現状維持が治療の目的となりますが、日常生活が困難になるくらい視力低下が進行してしまう事もあります。そのため、早期発見と適切な早期治療が必要です。糖尿病と診断された方は、定期的に眼底検査を受けていただくことをおすすめします。